我が家は3階建てで、寝室にしている子ども部屋が3階、リビングが2階です。
子ども部屋は狭く、リビングと離れていたので、赤ちゃんの寝室レイアウトには悩みました。
しかも、夫婦はベッド派ですが、赤ちゃんはお布団にしたかったのです。
赤ちゃんが安全に寝られる環境を整えるには、SIDSや窒息を防止するための知識も必要となります。
今回は、そんな我が家の赤ちゃん寝室事情についてまとめました。
赤ちゃんが安全に寝られる寝室の最低条件
まずは、赤ちゃんが安全に寝られる寝室の最低条件について考えてみましょう。
大事なのは、SIDSと窒息の予防です。
SIDS(乳幼児突然死症候群)の予防
SIDSは、乳幼児突然死症候群といい、元気だった赤ちゃんが突然死してしまうことです。
原因は不明とされていますが、うつ伏せ寝、保護者の喫煙、ミルク育児だと危険性が高くなると言われています。
一説によるとうつ熱が原因ともされ、赤ちゃんの衣服の着せすぎにも注意喚起がされています。
赤ちゃんは体温調整が苦手なので、衣服でこもった熱を放熱しきれないというメカニズムです。
 娘 こぺ
娘 こぺあったかすぎるのは苦手…



大人の服より1枚少なめってよく言われるね!
窒息の防止策
SIDSだけでなく、窒息にも気をつけなければいけません。
赤ちゃん用の敷布団が固めな理由の一つは、うつぶせになっても、顔がうまって窒息しないようにするためです。
なので、大人用の柔らかいベッドで一緒に寝るのはやめておきましょう。
さらに、生後間もない赤ちゃんは自由に動けないので、顔にかかった布でさえも自分で払いのけられません。
なので、赤ちゃんが寝る場所の周りには、いらないものを置かないようにしましょう。
ぬいぐるみも危ないと言われています。
寝返りし始めた時が一番心配
寝返りできるようになると、かなり心配が増えます。



睡眠中でも無意識で寝返ったりする…



戻しても戻してもすぐ寝返る…
困り果てて調べてみると、アメリカ小児科学会では、赤ちゃんが自力で仰向けに戻れる(寝返りがえりできる)場合は寝返りしても戻す必要はないとの見解を出していました。
寝ている途中で寝返ることより、赤ちゃんが寝ている周りに危険なものがある方がよくないということです。



でも心配は心配だよ!
心配な時は、赤ちゃんが危険な状態になっていないか、お知らせしてくれるグッズを使うのがおすすめです。
呼吸しているか感知するベビーセンサーや、寝返りを感知するベビーカメラなどがあります。
実は、娘は出産後の入院中、呼吸が止まってベビーセンサーが2回なってしまいました。
たくさん検査したものの異常はなく、嘘か本当か、まだ子宮の中にいると思って呼吸し忘れた可能性が高いと説明されました。



37週でちょっと早めに生まれたからかな?



生まれたの忘れてた…Zzz
母子の退院も、病院からベビーセンサーをレンタルする目処がつくまで延びてしまいました。
けれど、待ってでもベビーセンサーを借りられたおかげで、何もないよりずっと安心して眠ることができました。
病院でのレンタルは、実際に呼吸が止まったり、早産児の場合に限られてしまうそうです。
ですが、市販でも、赤ちゃんの呼吸の動きを感知する製品が発売されているので、事前に購入できます。



買ってる友達も多かったよ!
SIDS&窒息予防で掛け布団はいらない代わりに
先ほどの対策で述べたとおり、安全性を最重視するなら、掛け布団やベビー枕は必要ないです。
でも、ベビー布団セットには、掛け布団やベビー枕がセットになっていますよね。



セットなら使ったほうがいいのかな??
枕は大人の場合、首の負担軽減のために使っています。
しかし、背骨がS字型の大人と違って、新生児はC字なので、そもそも枕が必要ありません。
その他には、頭の形を歪ませない対策としてもベビー枕の話題がよく出てきます。
しかし、窒息の危険性があることに変わりはないので、使うにしてもお昼寝で保護者がずっと見ていられる時間に限った方が良さそうです。
ちなみに、頭の形対策は他に、授乳や抱っこで左右どちらかからに接し方が偏らないようにしたり、向きと逆方向から話しかけるのもいいです。
同じく掛け布団も危険でいらないのなら、赤ちゃんはどんな格好で寝かせればいいのでしょうか?
新生児期は、つい最近まで子宮の中にいたので、包まれていた方が眠りやすいという説があります。
そこで登場するのがおくるみです。
おくるみの巻き方には、赤ちゃんの身体全体を包んだり、足だけ出したりなどの種類があります。



病院で助産師さんも教えてくれた!
おくるみは、モロー反射という、外部刺激に驚いて両手を万歳する原始反射への対策にもなります。
反射なので悪いことではないのですが、目を覚まして泣いてしまうこともあるのが厄介です。
ちなみに、おくるみ以外の対策は、少し横向きに置いてから寝かせたり、手と足をそっと抑えてあげるといいです。
おくるみでうまく赤ちゃんを包めればいいのですが、私は教えてもらってもなかなかうまくできませんでした。



股関節脱臼が怖くてちゃんと包めなかった…
そこで、おくるみの代わりに見つけたのが、スワドルアップです。
スワドルアップは、チャック式のおくるみで、赤ちゃんが安心して眠れるように開発されました。
夜泣き対策として有名で、奇跡のおくるみとも言われています。
生地やステップごとに種類があり、足だけチャックを開けるといった使い方もできるので、部屋の温度による調整がしやすいです。
私は結果としてスリーパーを購入したのですが、寝かしつけの楽さではスワドルアップの方がよかったかなとちょっと後悔しています。



スワドルアップの方がすんなり寝てくれそう!
私が買ったスリーパーとは、パジャマのような、お布団のような、ベストの形をした着る寝具です。
赤ちゃんは手足で放熱して体温調整をしているので、手足が解放できるスリーパーを選びました。



SIDS対策にもなりそう!
スリーパーを買うときは、足元にボタンがついているものを選ぶのがおすすめです。
裾がまくれあがって顔にかかってしまうと窒息の危険性があるからです。
スリーパーの中でも特にかわいくておすすめのブランドは、ハルウララやケラッタです。
特にハルウララは出産祝いにも選ばれるくらい、柄がかわいくておすすめです。



スリーパー着てる娘ほんとかわいい!
狭い寝室ならミニベビーベッド
では、我が家の寝室事情についてご紹介します。
昼間のリビング事情についてはこちらの記事をご覧ください。
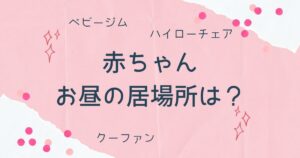
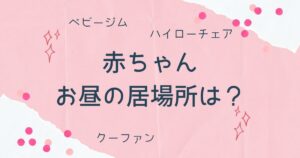
我が家は生後3ヶ月ごろに一軒家に引っ越したのですが、それまでは賃貸の狭い1LDKに住んでいました。
1LDK時代は、昼も夜もベビーベッドに寝かせていました。


ベビーベッドは高さがあるので、おむつ替えのお世話がしやすかったです。
引っ越し準備でほこりが心配な時期も心配がありませんでした。
購入したミニベビーベッドは、ベッドとしてだけでなく、机や棚など5通りに変形する優れものです。
よくあるベビー布団セットは買わずに、ベビー敷布団だけを2つ(洗い替え用含む)購入しました。



2つ買うのがあとで役に立つよ!
こちらの敷布団は、中身の固綿マットが分割されているので、おしっこがかかっても洗うのが簡単です。



女の子でもおむつ替えで噴射されるとは知らなかった…
でも実際は、敷布団に防水パッドと防水シーツを巻いていたので、敷布団まで洗うことはほぼ無かったです。
ベビーベッド卒業の時期
ベビーベッドはいつからいつまで使えるのでしょうか?
一応、ベビーベッドの対象年齢は24ヶ月まで、ミニベビーベッドは1歳ごろまでが多いです。
しかし、実際はそれよりも早く卒業することが多いです。
調べてみると、寝返りするようになると、木製ベビーベッドの柵の隙間に手足を突っ込んでしまうのが気になる方が多かったです。
ベビーベッドガードを設置したくなりますが、窒息予防の観点からは推奨されていません。



安全第一ならベッドには何も置かないのがいいんだよね!
困ったのですが、赤ちゃんが自分でベビーベッドの柵に手足を突っ込んでしまってもそこまで心配はいらず、
親が驚いて戻そうと、急に手足を引っ張ってしまう方が危険だそうです。



慌てずに手足を戻してあげなくちゃ!
気になるようなら、木製ではなく、メッシュタイプのベビーベッドがおすすめです。
また寝返りの後、つかまり立ちをするようになる頃も、危ないのでベビーベッドを卒業する方が多いです。
我が家は部屋の関係で、省スペースなミニベビーベッドを購入する予定でした。



ミニベビーベッドは1歳までだし、柵に手足突っ込むのも怖いな…
そこで、我が家では生後3ヶ月での引っ越しを機に、ミニベビーベッドを卒業することに決めました。
結果としては、ベビーベッド卒業のタイミングとしてはちょうどよかったです。
動き回るようになると、寝相とは思えないほど動くようになったからです。
3ヶ月での卒業は出産前から決めていたので、ミニベビーベッドは、5wayに変形できるものを選びました。
キッズテーブルや収納棚など5通りに変形するので、卒業後も長く使用することができます。
フローリングに夫婦はベッド&赤ちゃんだけ布団
引越し後は、5畳の子ども部屋を寝室にして、親子3人で寝ることにしました。
問題になったのは、私たちはベッド派なので、寝具をどうするかでした。
大人がベッド派の場合、大人用ベッドにベッドガードを設置して一緒に寝る方法が思い浮かびます。
しかし、大人用ベッドのベッドガードは、生後18ヶ月未満の使用はNGとされています。
ベッドとベッドガードの隙間に赤ちゃんが入りこんでしまい、窒息した事故が起こってしまったからです。
アメリカ小児学会でも、同じ部屋で寝るのが好ましいが、同じベッドで寝てはいけないとされています。
それなら私たち夫婦はベッド、赤ちゃんはミニベビーベッドを卒業してフローリングにお布団が一番よかったのですが、
そもそも部屋が狭すぎて、大人用ベッド2台とベビーベッドが入りませんでした。
なら大人を布団にするしかありませんが、新しく布団を買い直すのも、マットレスを眠らせておくのも勿体無いです。
なので、マットレスをそのまま敷くことにしました。



ギリギリで入ったけどこの向きしか無理だった…


ただカビが怖いので、除湿シートを敷いて、日中はマットレスを上げるようにしています。
部屋のサイズに余裕があるなら、すのこベッドを買って一番低くするのもおすすめです。
レイアウトは、大人のマットレスの頭側に赤ちゃんのお布団を置きました。


親の掛け布団が落ちて、赤ちゃんにかぶって窒息するのが怖かったからです。
掛け布団が気になる場合は、大人のベッドにベッドガードをつけて掛け布団が落ちないようにするのもおすすめです。
また、トイレで起きた時にうっかり赤ちゃんを踏まないかも心配だったので、ドアから一番遠いところに子どもの布団を敷きました。
子どもの布団は、ミニベビーベッドで使っていたベビー敷布団を2つ繋げて使っています。
シーツは大人用のシングルサイズのシーツを2つ折りにして巻いたらちょうどでした。
広々としているので、動きを制限することなく自由に寝ています。



寝ながらそんなに動ける!?ってくらい縦横無尽!



広いから壁にぶつかりにくくて嬉しい!
最大の失敗は、お布団をベビーサークルで囲まなかったことです。
成長するにつれ、だんだんマットレスを登ってくるようになってしまいました。
1歳半の今では、気がつけば隣で寝ていたりします。
ただ隣で寝ているだけならかわいいのですが、娘は寝相がひどく悪いです。
親の身体の隙間に手を入れてきたり、足でゲシゲシ蹴ってきたりして、こちらは起きてしまいます。



毎晩蹴られて困るけど朝の笑顔で帳消しにしてくる!
今から寝室づくりをする方は、ぜひベビーサークルでお布団を囲んでください。
私は今からでも設置したいのですが、絶対ギャン泣きで逆に大変だよと夫に反対されています。
設置するならサイズ調整のできるベビーサークルがおすすめです。
ドアのついているものだと出入りしやすくて、なお良いです。
リビングと離れてるならベビーカメラ必須
我が家では、娘には先に晩ごはんを食べさせて、18時ごろに寝かせています。
寝かしつけが終わったら大人の晩ごはんなので、寝室にずっといるわけにはいきません。
なので、赤ちゃんの様子が見られるようにベビーカメラを導入しています。
2階のリビングは3階の寝室とは離れていますが、ベビーカメラのおかげで泣いてもすぐに駆けつけることができています。
最近では、ベビーセンサーが一緒になっているものも発売されているので、より安心して大人の時間を過ごすことができますよ。
ベビーモニターについては、こちらの記事で詳しく比較しています。
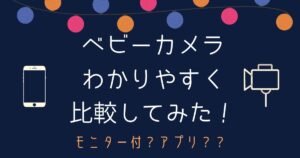
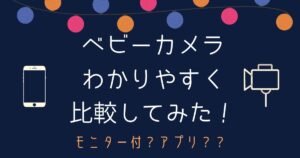

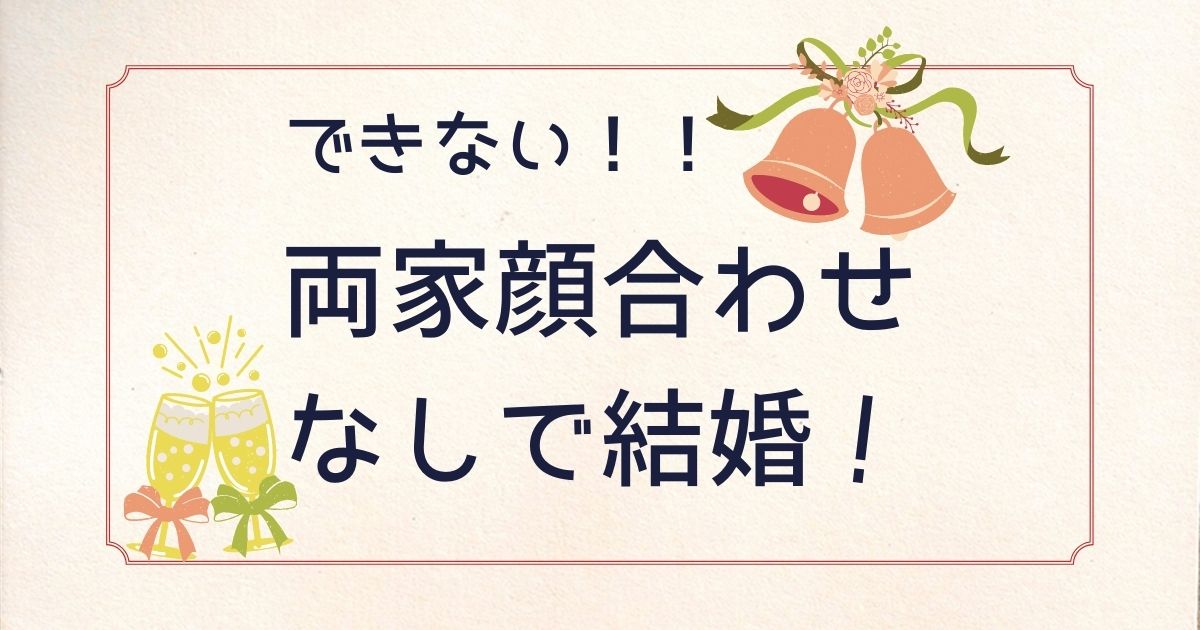
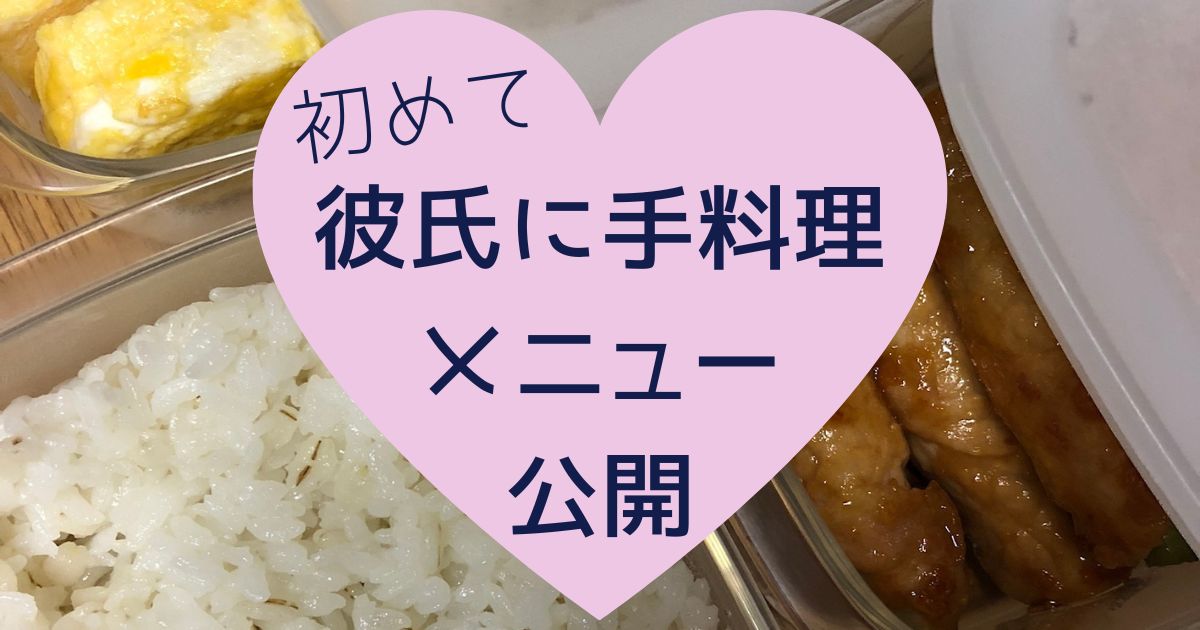
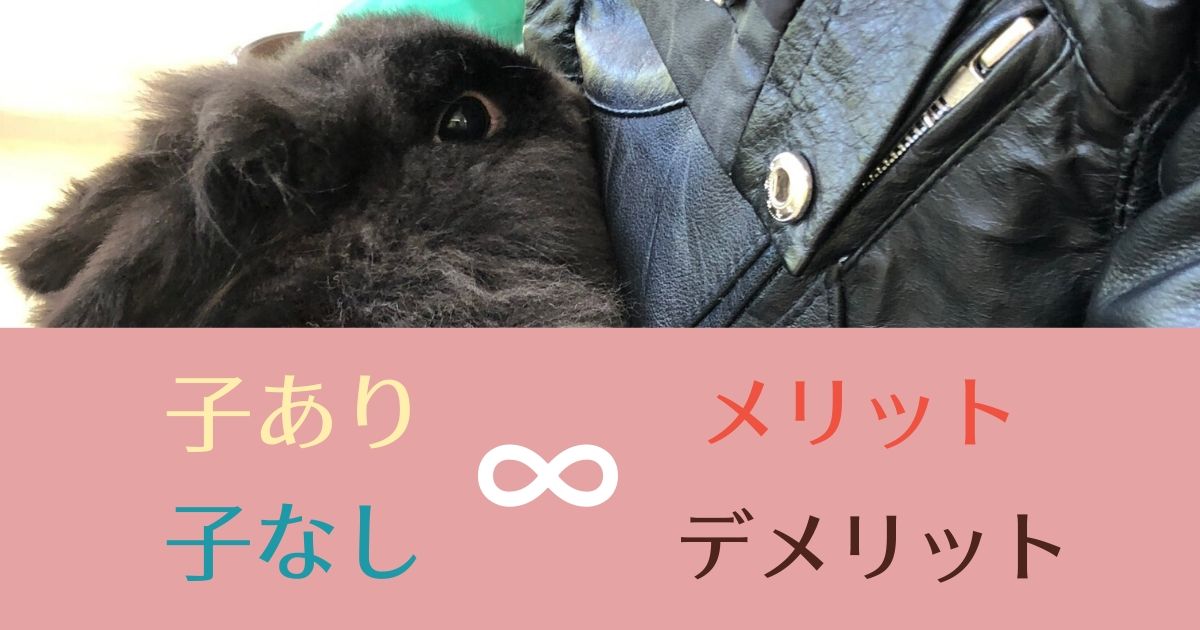
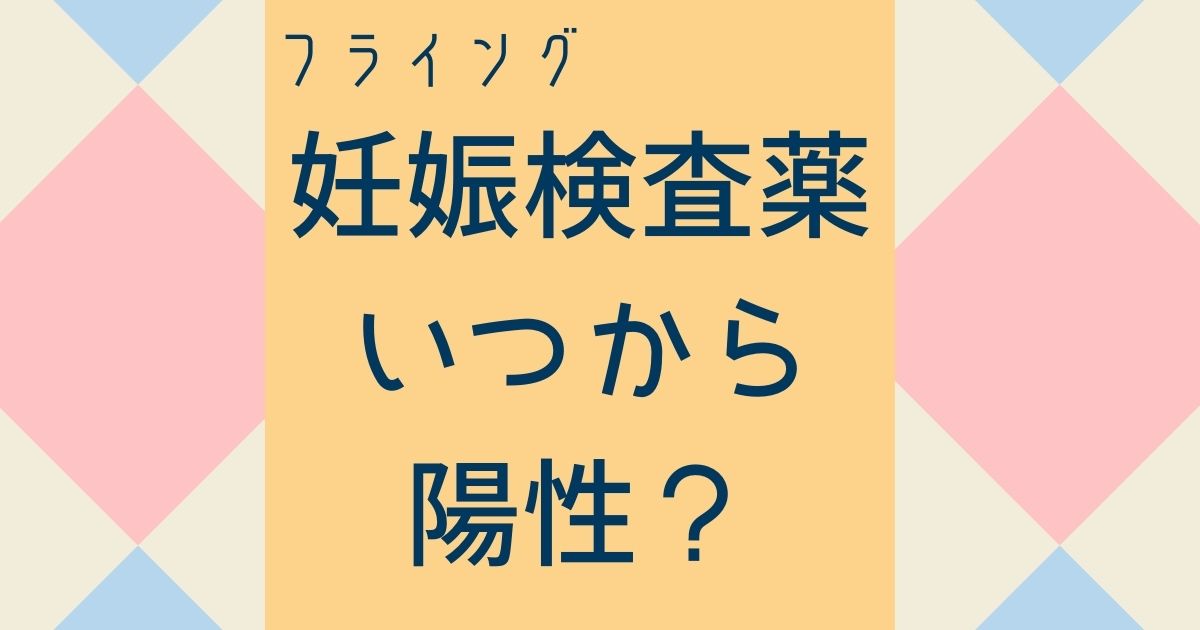
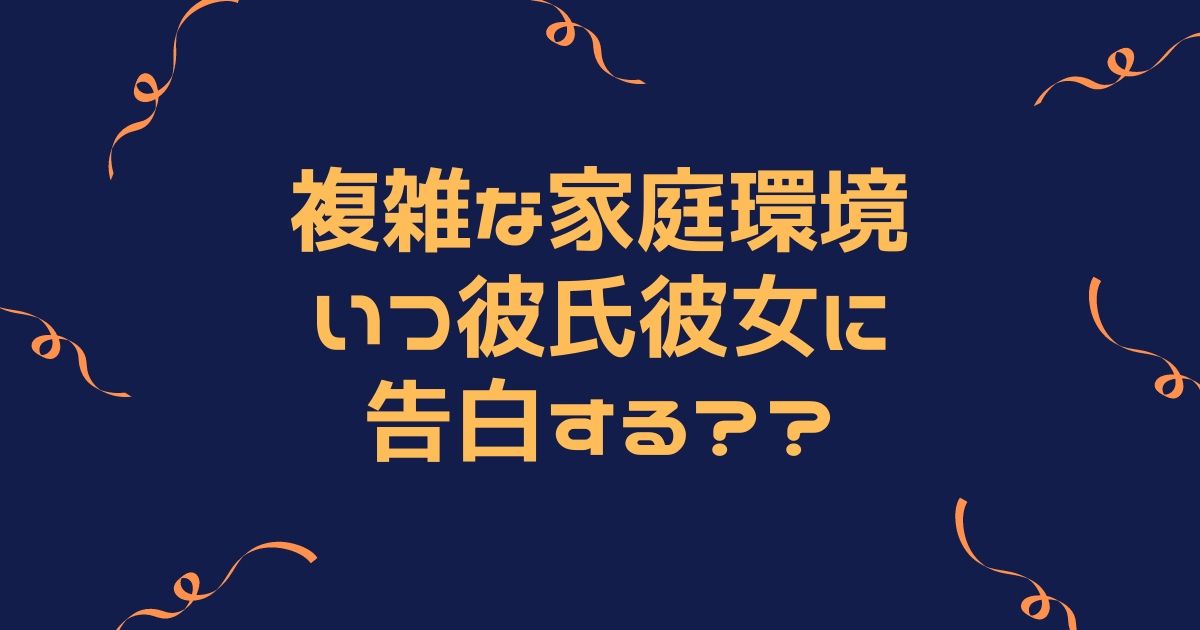
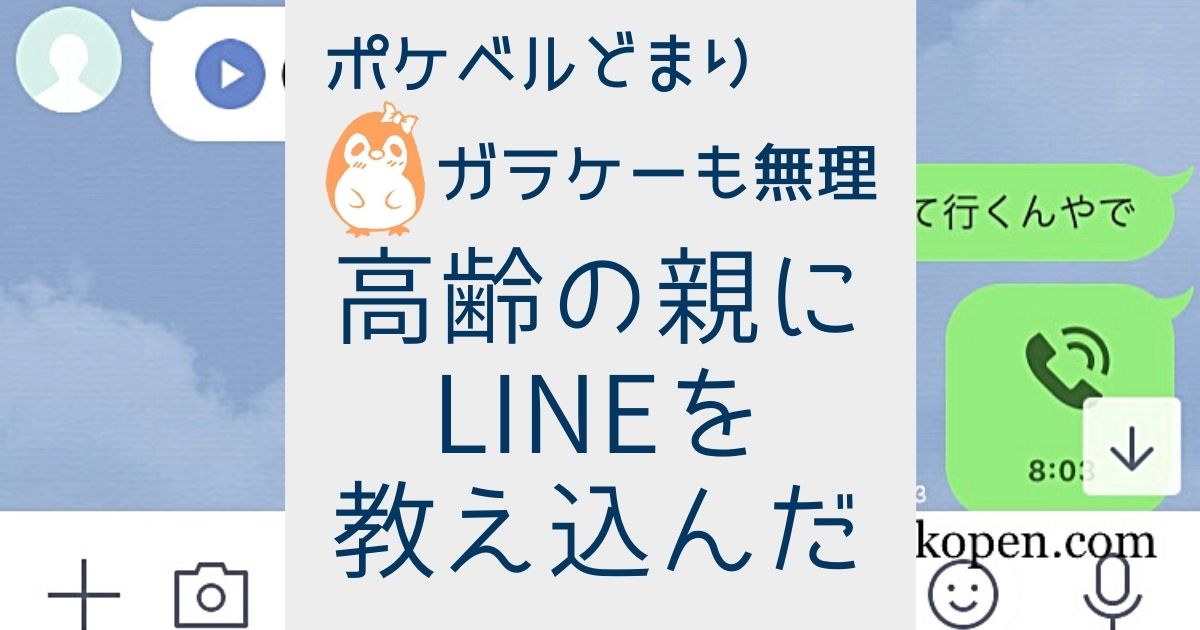

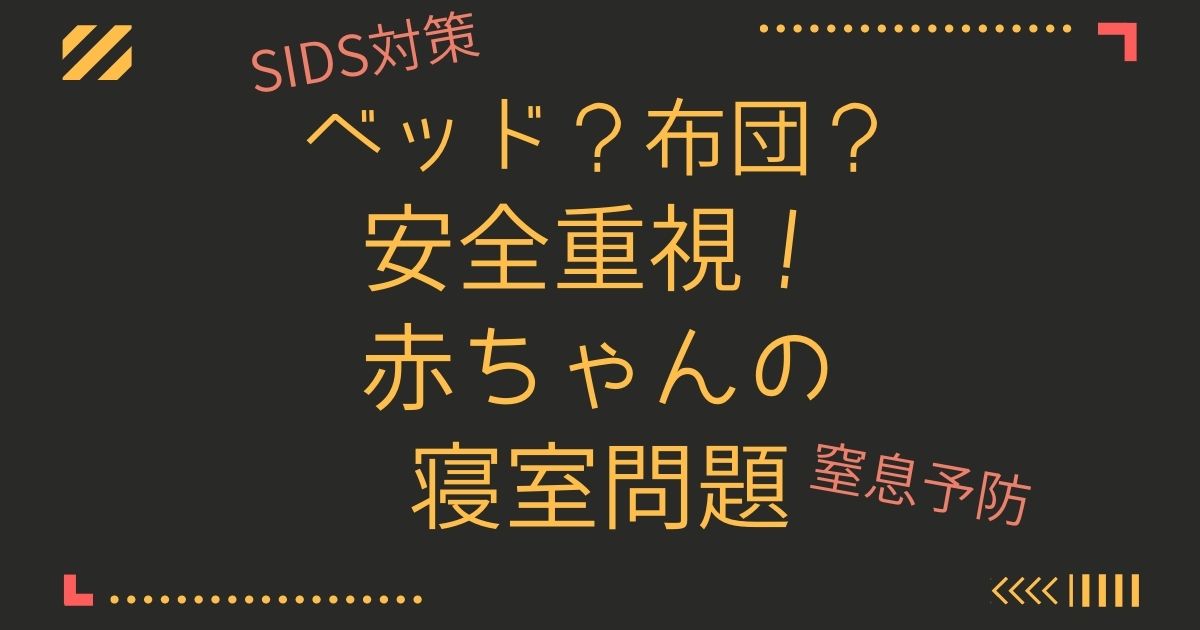














コメント