出産後、母子がおうちに帰ってきたら、沐浴をしなければなりません。
赤ちゃんをお風呂に入れるのに便利なのがベビーバス。
空気タイプや床置きタイプ、折りたたみタイプなどたくさんの種類があって迷ってしまいますよね。
とはいえ、沐浴って1ヶ月程度のこと。
できるなら沐浴卒業後も、長く使えるベビーバスを買いたいところです。
私も妊娠中に、長く使えるベビーバスを探して調べまくったので、比較表を作ってみました。
結果、沐浴〜卒業後までずっと使えるベビーバスを発見し、1歳半でも現役で使っています。
そのほか、赤ちゃんが夢中になるお風呂用おもちゃも紹介します。
新生児はベビーバスで沐浴
まずは、なぜ新生児は沐浴なのかを軽くまとめてみましょう。
生まれたばかりの赤ちゃんは、沐浴(もくよく)をします。
沐浴とは、大人の浴槽は使わず、ベビーバスを使って赤ちゃんを洗うことです。
へその緒が取れていない、生後間もない赤ちゃんは抵抗力が弱く、感染症にかかりやすいです。
なので、細菌感染の危険性が高い大人の浴槽を使わず、赤ちゃん専用のベビーバスを用意します。
ちなみに、母親自身も出産後1ヶ月程度、入浴禁止&シャワーのみとされます。
沐浴をする場所は、洗面台以外にもキッチンのシンク、お風呂場でも可能ですが、洗面台やシンクをそのまま沐浴に使うのは衛生面でNGです。
洗面台って高さもあるし、沐浴にぴったりですが、大人が歯磨きや洗顔をするので、雑菌が多く汚い場所なんです。
沐浴のたびに掃除や消毒するのも逆に面倒なので、ベビーバスまたは下記のような沐浴マットを用意するのがおすすめです。
長く使えるベビーバス比較
ベビーバスって種類もたくさんあるし、まだ見ぬ赤ちゃんのことを考えて選ばないといけないので悩んでしまうと思います。
赤ちゃんのお風呂は毎日のことなので、ベビーバスを選ぶ際は親の負担にならないことを基準にすると選びやすいです。
実際に、ベビーバスを比較していきましょう。
空気タイプのリッチェルのベビーバス
沐浴用のベビーバスとして一番人気なのは、リッチェルのベビーバスです。
リッチェルのベビーバスは調べてみると、Wとプラス(新製品)の2種類がありました。
違いは、Wが対象月例が3ヶ月ごろまで、プラスが6ヶ月ごろまででした。
また、プラスの方はエアーポンプ内蔵で、空気入れが簡単です。
小さめでかわいいラッコハグ
あまりのかわいさに人気急上昇中のベビーバスがラッコハグです。
リッチェルのベビーバスと比較して少し小さめサイズなので、洗面台で沐浴する方やお風呂場が狭い方におすすめです。
赤ちゃんの成長に合わせて、沐浴や待機場所、プールとしてなど5Wayで活躍します。
床置きタイプの永和のベビーバス
エアータイプの他に、安定感のある床置きタイプのベビーバスもあります。
まずおすすめなのは、永和のベビーバスです。
赤ちゃんがずり落ちてしまうのを防止するストッパーがお尻の部分にあります。
別売りのバスネットを購入すれば、代わりに赤ちゃんの頭を支えてくれて、親の負担が減ります。
コンパクトサイズのシュナグル
家庭用のシンクにも入るコンパクトサイズのベビーバスがシュナグルです。
おしりストッパーが赤ちゃんを支えてくれるので、親の腕の負担が軽減されます。
必要なお湯の量も2Lでいいので、節水にもなります。
本体の脚裏にはゴムの滑り止めがついており、安全対策もバッチリです。
折りたたみタイプのストッケのフレキシバス
ベビーバスで場所を取りたくないという方には、省スペースで保管できる折りたたみタイプがおすすめです。
妊娠中に行ったファミリアの沐浴体験では、ストッケのベビーバス、フレキシバスを使用していました。
フレキシバス単体だと、非力な私には少し辛かったので、別売りのニューボーンサポートを購入するとよさそうでした。
ベビーバス比較表
ここまで紹介したベビーバスを表にして比較してみました。
| 対象月齢 | サイズ | |
 リッチェルベビーバス | 新生児〜6ヶ月頃 | 約69 × 47 × 28 cm |
 ラッコハグ | 0ヶ月~2歳頃 | 約58 x 42 x 36 cm |
 永和ベビーバス | 0ヶ月~3ヶ月頃 | 約63 × 40 × 23 cm |
 シュナグル | 0ヶ月~12ヶ月 | 約60 x 39 x 36 cm |
 | 0ヶ月~4歳頃 | 約24 x 34 x 64 cm |
こちらの比較表を作った当時は、永和のベビーバスとふんわりバスネットを購入しようとしていました。
ですが、我が家では沐浴を卒業してからも役に立つをベビーバスを買いたかったので、もう少し検討してみることにしました。
ベビーバスでの沐浴卒業後に使えるグッズ
長く使えるコスパ最強のベビーバス探しには、沐浴卒業後の赤ちゃんのお風呂の入れ方についても考えなければいけません。
ベビーバスでの沐浴を卒業するのは、大体生後1ヶ月頃です。
母親の私も、1ヶ月検診でお医者さんから母子ともに浴槽での入浴が許可されました。
夫婦で協力できる場合は、沐浴後は赤ちゃんの洗い方と入浴に変更があります。
ワンオペの場合、さらに待たせ方も考えねばなりません。
こちらの記事で、3ステップに分けて、もう少し詳しく解説してグッズ探しをしているので参考にしてください。
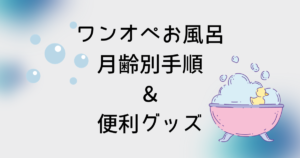
沐浴卒業後の赤ちゃんの洗い場
沐浴卒業後は、赤ちゃんの洗い方、入浴の仕方を考えるのがカギとなります。
ますは、ベビーバスなしでどうやって赤ちゃんを洗うかです。
費用のかからない方法だと、大人の膝の上で赤ちゃんを洗うやり方があります。
 妻 わこぺ
妻 わこぺでも、膝の上で洗うのはちょっと怖くてできなかった…
なので、私は赤ちゃんの身体の洗い場を作ることにしました。
洗い場には、引き続きベビーバスを使用してもいいですし、新しくお風呂マットを購入してもいいでしょう。
赤ちゃんを洗いやすいと評判が高いのはリッチェルのおふろマットです。
赤ちゃんを寝かせられるので、両手で洗ってあげることができます。
お尻の部分にお湯をためられて、赤ちゃんの身体が冷えにくい仕様になっています。
沐浴卒業後の入浴方法
次に、入浴の方法です。
入浴は大人と一緒に浴槽に入るのか、ベビーバスを引き続き使うのかがポイントになります。
なんにせよ、赤ちゃんは数センチの水位でも溺れてしまうので、決して目を離さないことが重要です。
また、湯船は割と滑りやすいので、下記のような浴槽に敷くマットを敷くのがおすすめです。
ずっと使える最強ベビーバスはこれ!
ベビーバスに悩みまくっていた時、LDKのベビーグッズ特集を読みました。
LDKは忖度なしの辛口レビューが好評の雑誌です。
毎年最新の商品レビューが発売されており、1冊持っておいて損はない雑誌です。
そのLDKに掲載されていて目をひかれたのが、ホエールバスタブです。
結局、ホエールバスタブが一番長く使えそうなベビーバスだと感じ、購入にいたりました。
すると、新生児期から1歳半の今でも大活躍してくれるコスパ最強のベビーバスでした。
ホエールバスタブのおかげで、沐浴中は身体を支える必要がなく、両手が使えて楽でした。
沐浴卒業後も、洗い場と湯船をベビーバスで兼用していました。
詳しくはこちらの記事でレビューしています。
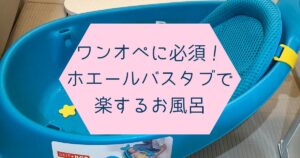
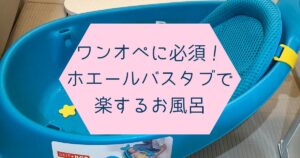
途中で、身体を洗っている間にベビーバスにお湯をためられるように、お風呂マットを買い足しました。
お風呂マットに購入したのはこちらです。
ホエールバスタブが少し大きめだったので、省スペースなこちらのお風呂マットを選びました。
使わないときは立てかけておけるので、場所も取らなくて良かったです。
娘が1歳半の現在、お風呂グッズで購入したのは、ホエールバスタブと手おけ、お風呂マットの3点だけです。
毎日使っているものだと考えると、すごくコスパの良い買い物ができたと感じています。
気分を上げるお風呂のおもちゃ
赤ちゃんも成長してくると、お風呂場であまり大人しくしてくれません。
なので、いくつかおもちゃを用意しておくのがおすすめです。
娘は、手おけを使って移し替え遊びをするのが好きです。
移し替え遊びといえば、モンテッソーリ教育でも有名ですよね。
下のようなおもちゃだと、仕掛けもあって、楽しんでくれやすいです。
こちらのおもちゃも娘のお気に入りです。
水鉄砲としてや、手おけで金魚すくいのような遊び方もしています。
海の生き物の名前も覚えられ、「今日は1つだけ持ってお風呂入ろうね」などといって数字の勉強にもなっています。
ずっと使えるベビーバスはこれ!
今回は、長く使えるベビーバスを探して、比較してみました。
たくさんの中から悩んで選んだホエールバスタブは、1歳半の今でも現役で、我ながら本当にいいお買い物をしたなーと思っています。
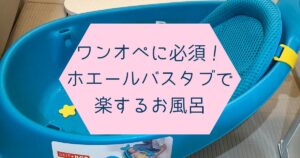
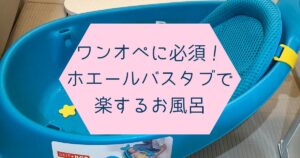
成長につれて買ったお風呂マットも、赤ちゃんを洗うのに固い床に置かずに済みました。
ずっとワンオペで子どもをお風呂に入れる予定のある方は、洗い方、入浴に加えて、赤ちゃんを待たせるグッズについても比較検討したこちらの記事もご覧ください。
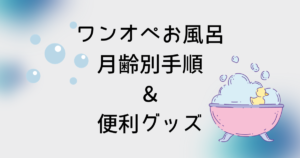
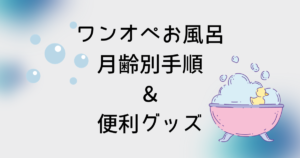

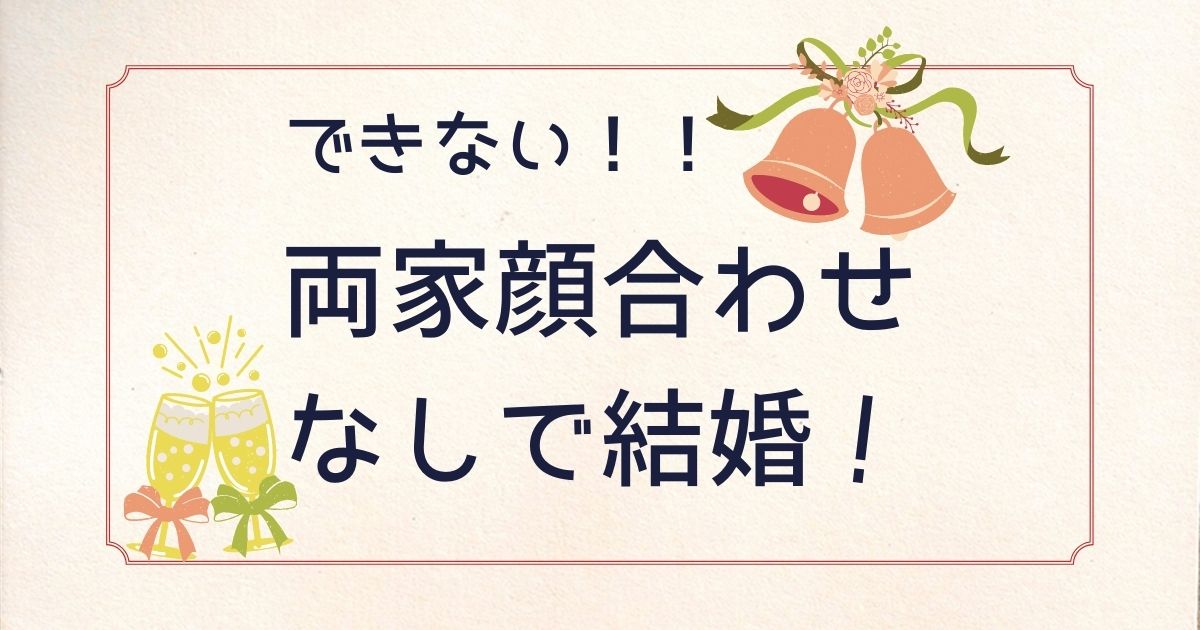
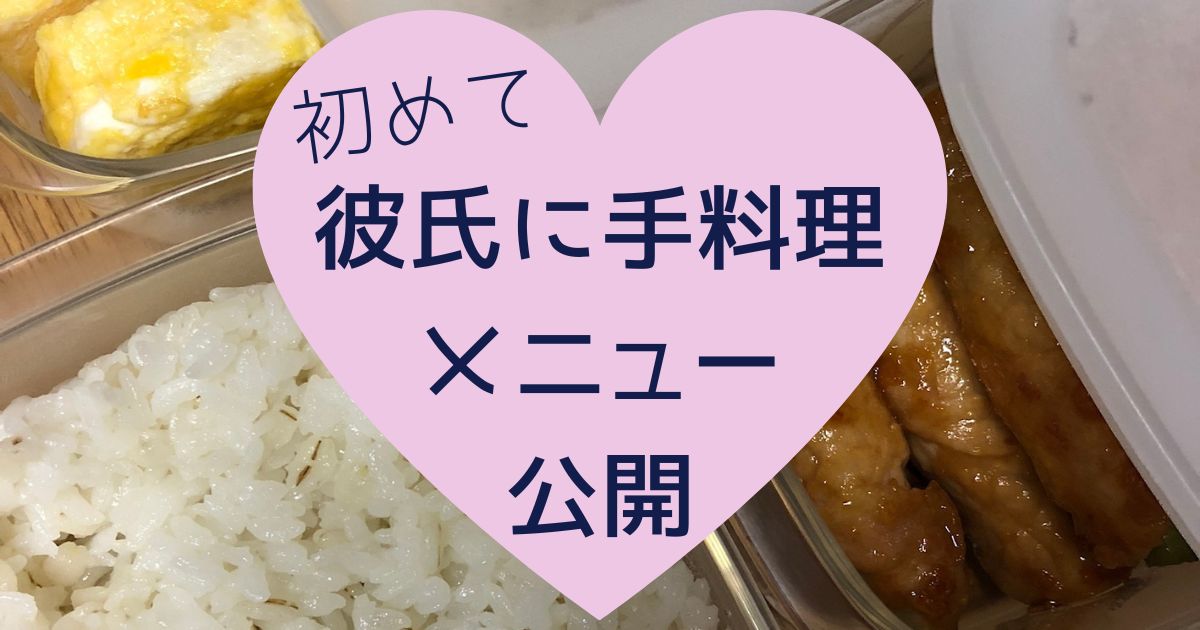
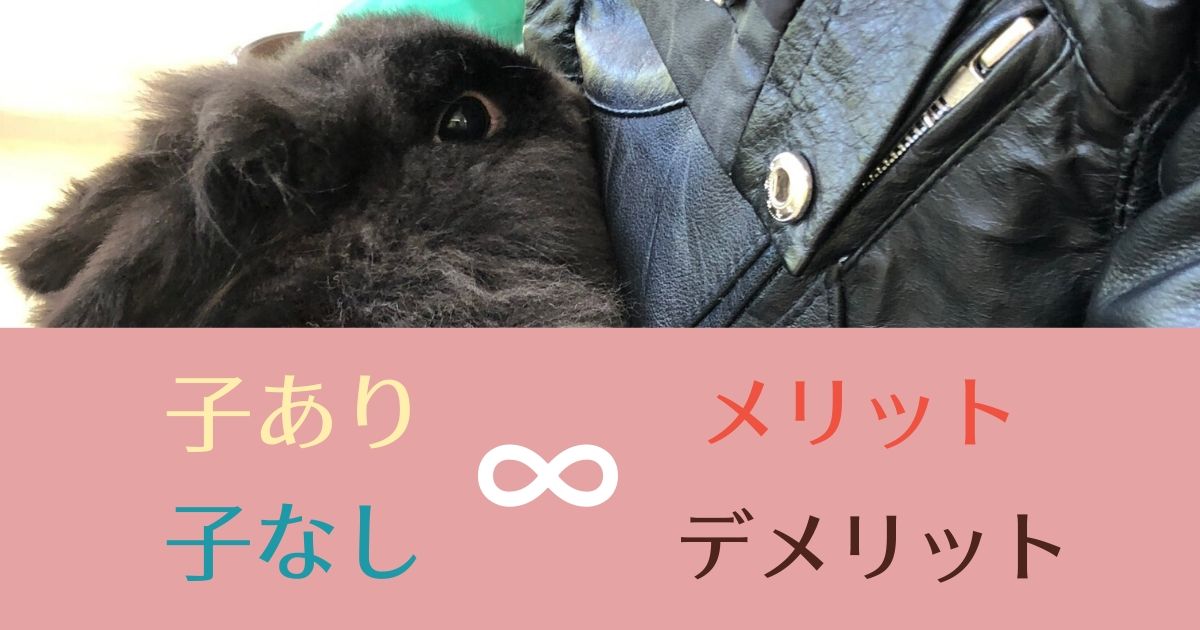
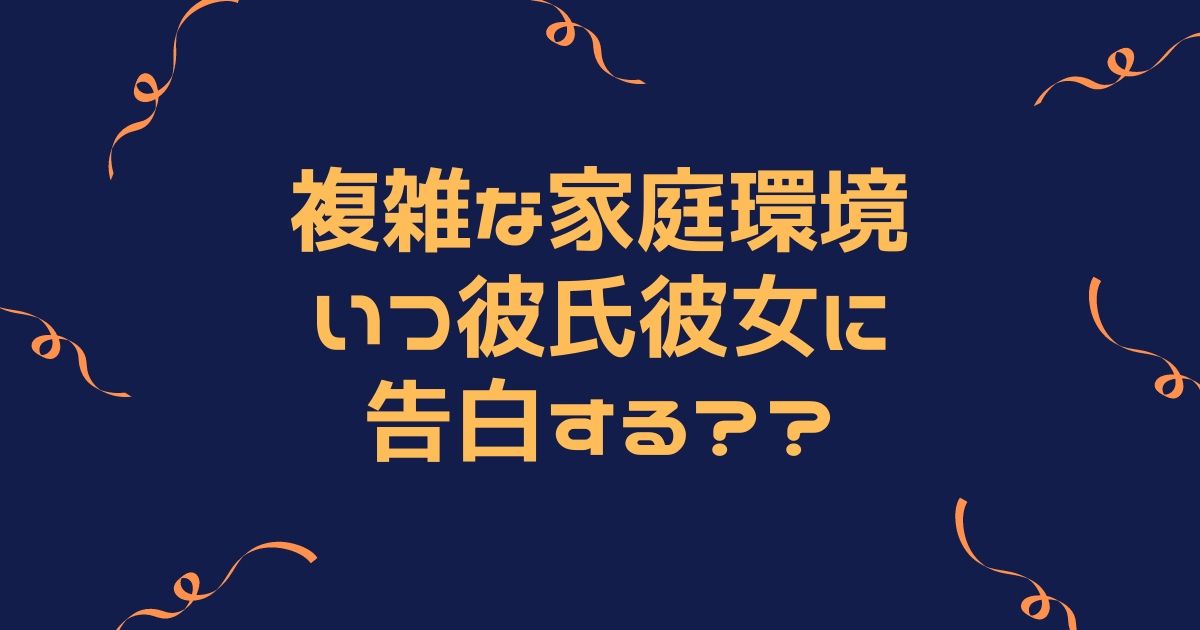
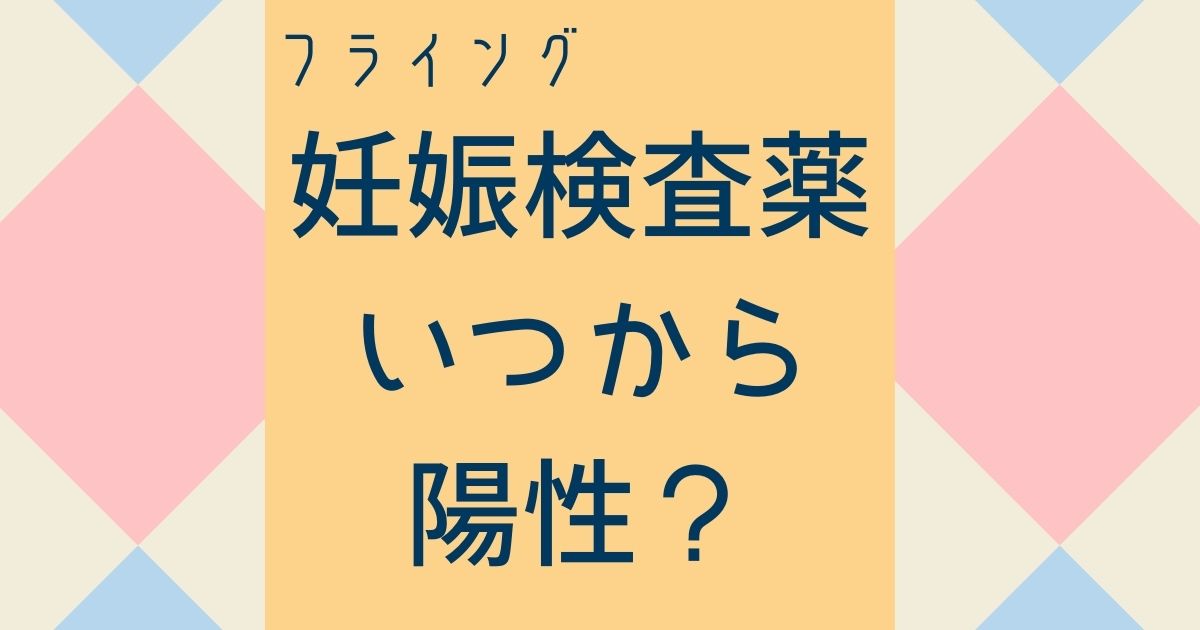
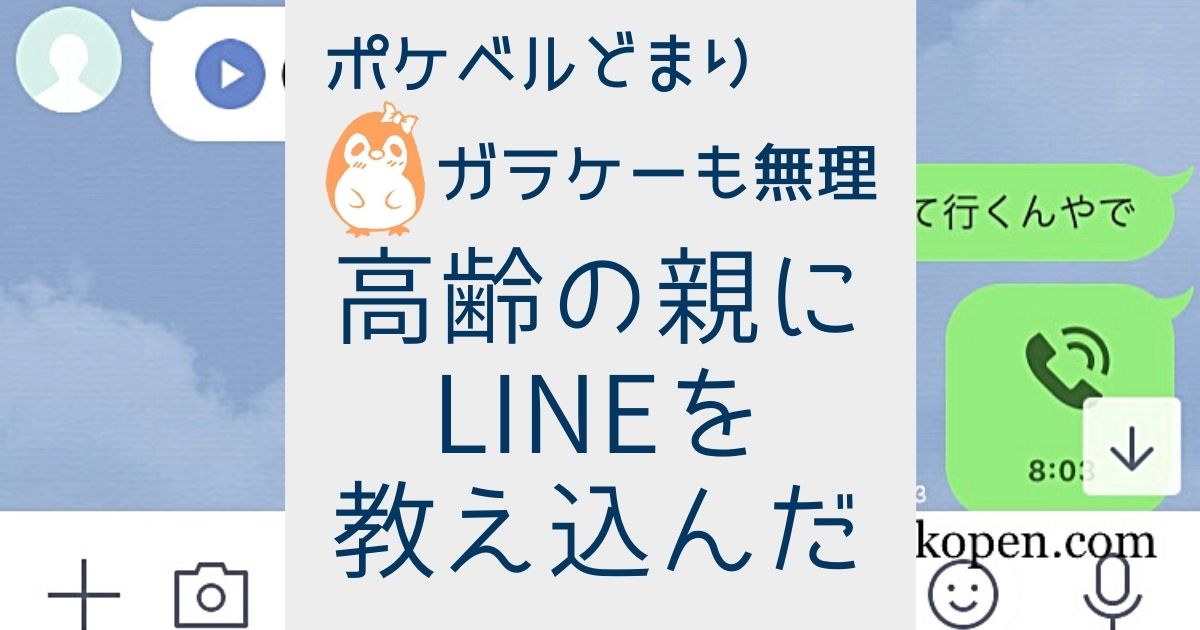

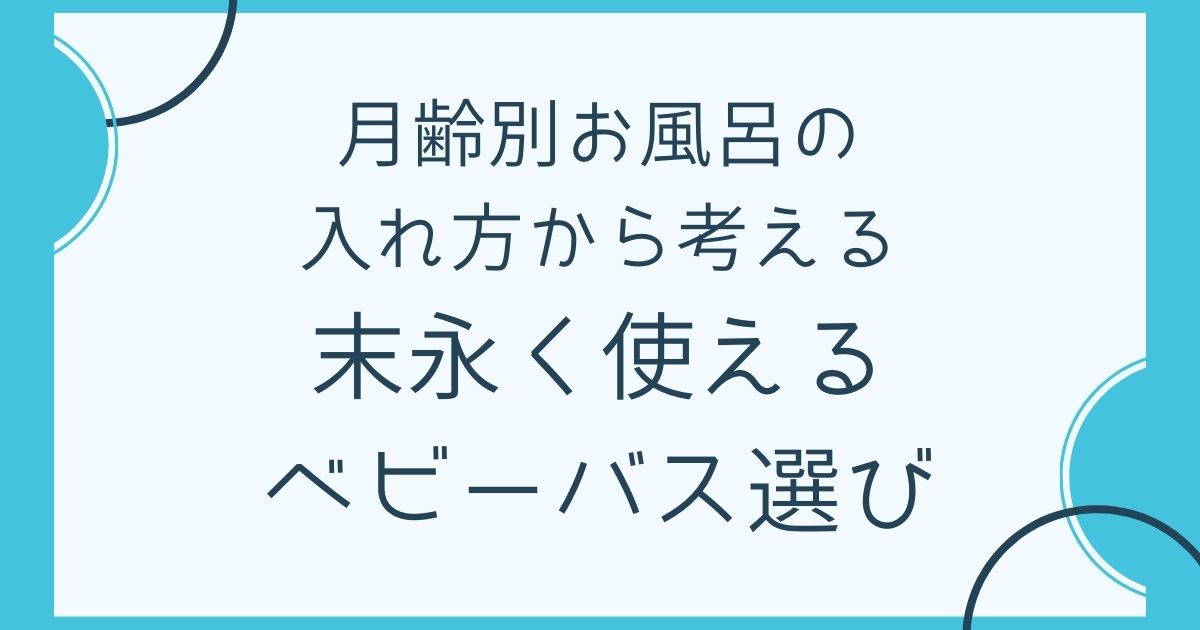















コメント