今ではネットで検索すれば美味しそうな料理のレシピが山ほど出てきます。
しかし、献立まで提案してくれるサイトはそう多くありません。
私も、料理ができるようになった後、一番困ったのは献立の立て方でした。
家族の健康も考えると、献立の栄養バランスも気になります。
そこで大型書店に行き、料理本の棚を端から端までチェックして献立の立て方に役立つ料理本を探して勉強をしました。
この経験が、新婚生活でかなり役に立ちました。
今回は、献立をどうやって決めるか悩んでいた私の手助けになった料理本をご紹介します。
食材の下ごしらえや保存方法など、基本的な料理の知識をおさらいしたい方はこちらの記事をどうぞ!
献立を考えたくない、思いつかないなら
まずは、もう献立のことは考えたくない、そもそも献立を思いつかないという方におすすめの献立本です。
決定版 ずっと使える「一汁二菜」献立帳

決定版 ずっと使える「一汁二菜」献立帳 定番おかずで組み合わせる「主菜+副菜+汁もの」
こちらの献立本は、一汁二菜の献立が数多く載っています。
家庭科で習った一汁三菜が理想なのはわかっていますが、共働きとかだと正直無理ですよね。
こちらの献立本はメインになる主菜と汁物、副菜一つという、無理なく続けやすい献立が提案されており、実生活に即した献立本だと言えます。
たくさんの献立レパートリーを和洋中さまざまな料理の専門家が紹介してくれています。
お肉がメインの献立、お魚がメインの献立、ご飯ものが主役の献立など、その日に使いたいメイン食材から献立を選べるのもポイントです。
また、材料別の細かい索引だけではなく、炒め物や揚げ物、煮物など、調理別の索引もあり、気分によっても献立を選ぶことができます。
さらにこの献立本では、献立のみならず、段取りのタイムスケジュールも表として掲載されています。
こっちの副菜はあっちに載ってた副菜に変えてもOKなど、献立のアレンジも紹介されており、応用がきくのもポイントです。
そして、もう一つこの献立本のおかげで助かるポイントが、汁物のレシピが豊富なことです。
私は汁物のレパートリーが少なく、とりあえずお味噌汁作っておくか…と逃げてしまうのが献立づくりの悩みでした。
このような悩みもカバーしてくれるので、こちらの献立本は、献立の立て方に悩んでいる方の最初の一冊にもってこいの本としておすすめです。
かなり分厚く、重い本なのでネット通販での購入がおすすめですよ。
健康を気遣える栄養バランスの取れた献立に悩んだら
単に食事と言っても、食べられればいいというわけではなく、年齢を重ねるにつれだんだんと健康を気遣った食事を心がけたいですよね。
そこで、栄養バランスを気遣った献立を知りたい方におすすめなのが、こちらの献立本です。
聖路加国際病院の愛情健康レシピ

聖路加国際病院の 愛情健康レシピ
健康における食事の重要性を一番に考えているのは誰だと思いますか??
それは、病院の栄養科の方たちです。
聖路加国際病院では、栄養バランスだけを重視しがちな病院食において、おいしさにもこだわっており、入院患者の方も「入院中の食事が楽しみ!」と言うほど評判です。
病院のご飯というと、味気が無いとか質素とかあまり良いイメージが無いですが、こちらで紹介されている献立のメニューはどれも美味しそうな料理ばかりです。
私も実際に作ってみましたが、確かにおいしかったです。
けれど、働き盛りの年齢の夫には量がちょっと少ないかなということもあるので、時には食材の量を増やしたりしています。
こちらの献立本の冒頭には、毎日の料理で気を付けるべきポイントも載っています。
毎日の食事が身体をつくると考えると、日々の献立にも気を遣いたいですよね。
健康のため栄養バランスが整った献立づくりに悩む方におすすめの献立本です。
女子栄養大学の毎日おかず

女子栄養大学の毎日おかず;食材からひける、献立もついてる : おかず400品夕ごはん270献立
栄養バランスを気遣った献立をもっと知りたい方には、女子栄養大学の料理本もレビューが好評でおすすめです。
料理のレシピ400品と献立が270通りも載っていますよ。
献立を考える基本のポイントを知りたいなら
次に紹介するのは、自分でも悩まずに献立を決められるように、献立の立て方を考えるときの基本的なポイントが学べる本です。
1日にとりたい食品と量がわかる きほんの献立練習帳

1日にとりたい食品と量がわかる きほんの献立練習帳
1日にどんな食材をどのくらい食べればいいのかという視点から解説してくれているので、栄養バランスを重視したい方にもおすすめです。
 妻 わこぺ
妻 わこぺタンパク質〇〇グラム摂った方がいいとか言われてもわからないから、食材で示してくれるのありがたい!
栄養バランスをとるといっても、晩ご飯だけ気遣っても不十分で、朝ご飯と昼ご飯も含めて、1日の中でどのように栄養バランスを整えればいいのかを教えてくれる献立本です。
献立レパートリーを増やすレシピ本に困ったら
定番の献立は立てられるようになったけど、レパートリーを広げてアレンジを楽しみたいというかたにおすすめの料理本をご紹介します。
藤井恵さんの体にいい和食ごはん


藤井恵さんの体にいい和食ごはん
こちらのレシピ本は、体にいい和食ごはんをテーマに、定番料理とは一味違うレシピが数多く掲載されています。
味噌やお酢などの発酵食品である調味料を使った料理や、魚介や大豆、海藻を使った料理、野菜をたっぷり食べられる料理など、健康にやさしいおかずが100品以上!
普通のレシピ本だとあまり無い観点のレシピが豊富です。
私もこのレシピ本を参考に、みそ肉じゃがを作ってみたのですが、いつもの肉じゃがの調味料を少し変えるだけの簡単アレンジで、とても美味しくなって、感動しました。
新発見があるレシピが多く、献立のレパートリーを増やすのにおすすめなレシピ本です。
藤井恵さんの体にいいごはん献立


藤井恵さんの体にいいごはん献立
先ほどの料理本の巻末にも少し献立が載っているのですが、もっと献立中心の本をお探しの方には、同じ作者のこちらの献立本がおすすめです。
美味しいだけではなく、栄養バランスにも配慮したバランスの良い食事の献立が多数掲載されています。
毎日続けられる手軽さもこの献立本のポイントです。
晩ご飯の献立に簡単に一品追加したいなら
晩ご飯の献立を考えていて、副菜があと一品思いつかない時に大活躍する本をご紹介します。
たった10分でできる副菜図鑑


たった10分でできる副菜図鑑 (オレンジページブックス)
オレンジページ出版の副菜に特化したレシピ本です。
タイトルの10分で作れるという名の通り、どのレシピも簡単で、ささっと副菜を1品追加することができます。
食材別の索引があるのでレシピを探しやすく、一つの食材で5~11品のレシピが紹介されいます。
なので、毎日このレシピ本を参考にしても、献立がかぶってしまうということがありません。
野菜だけではなく、豆腐や卵の副菜レシピも豊富ですし、お味噌汁やスープといった汁物も和洋中さまざまなレシピが掲載されています。
1冊持っておくと、もう献立の副菜に悩むことはありません。
デパ地下みたいなごちそうサラダ ベストレシピ 決定版


栄養バランスの整った献立といえば、野菜たっぷりのサラダが欠かせません。
とはいっても、私はサラダのレパートリーが少なく、野菜にオリーブオイルと塩をかけてごまかすばかりでした。
そんな時に見つけたこの本には、デパ地下で売っているような、食欲をそそるサラダのレシピがたくさん掲載されていました。
おしゃれでありながら、普通に家にある材料で作れる簡単なレシピだというのもポイントが高いです。
別冊で手作りドレッシングの作り方も掲載されているので、一冊あればもうサラダには困らないのでおすすめです。
今回は、毎日頭を悩ませる献立の決め方の役に立つ本をご紹介しました。
献立づくりって毎日のことだし、何も思いつかない日もあって当然だと思います。
最初は献立本に載っている献立をそのまま真似するだけでもいいので、献立を考える手間を省いてストレスを無くしましょう!
新婚生活を控えている方にもおすすめです。
この記事が、献立をどうやって決めるか悩んでいる方の手助けになっていれば幸いです。
また、献立本ではなく、自分で料理を作りながら学びたいという方には料理教室もおすすめです。
最近では、CookLIVEこちらの料理教室では作り置きを専門的に取り扱っているので、休日に取り組みやすく、忙しい平日の手助けにもなります。
都度払い可で料金も安いですし、自宅から参加もできるので、男女を問わず気軽に料理教室で学ぶことができます。
>>オンライン料理教室CookLIVE

また、お金にも余裕がある方なら、あのライザップの料理教室もあります。
プロによるマンツーマンの指導により、短期集中で料理を覚えることができます。
献立力の上達に特化したコースもあり、自分のレベルに合わせて選ぶことができます。
まずは無料で料理力診断もできますよ。
>>一流料理人があなたの劇的な料理上達にコミット!【RIZAP COOK】
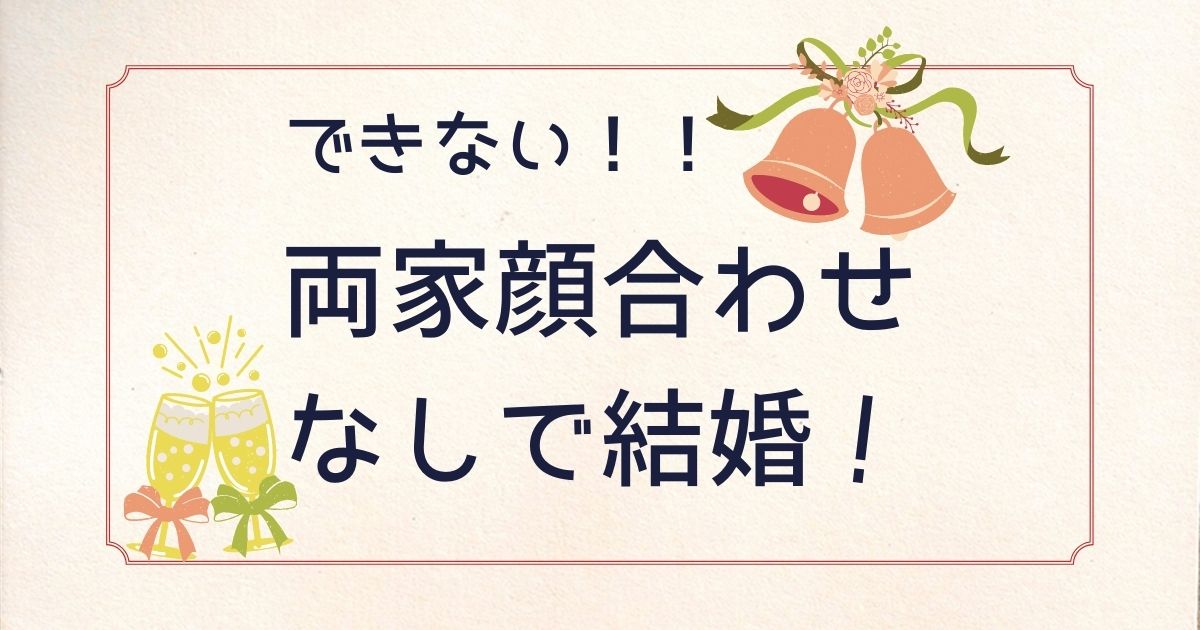
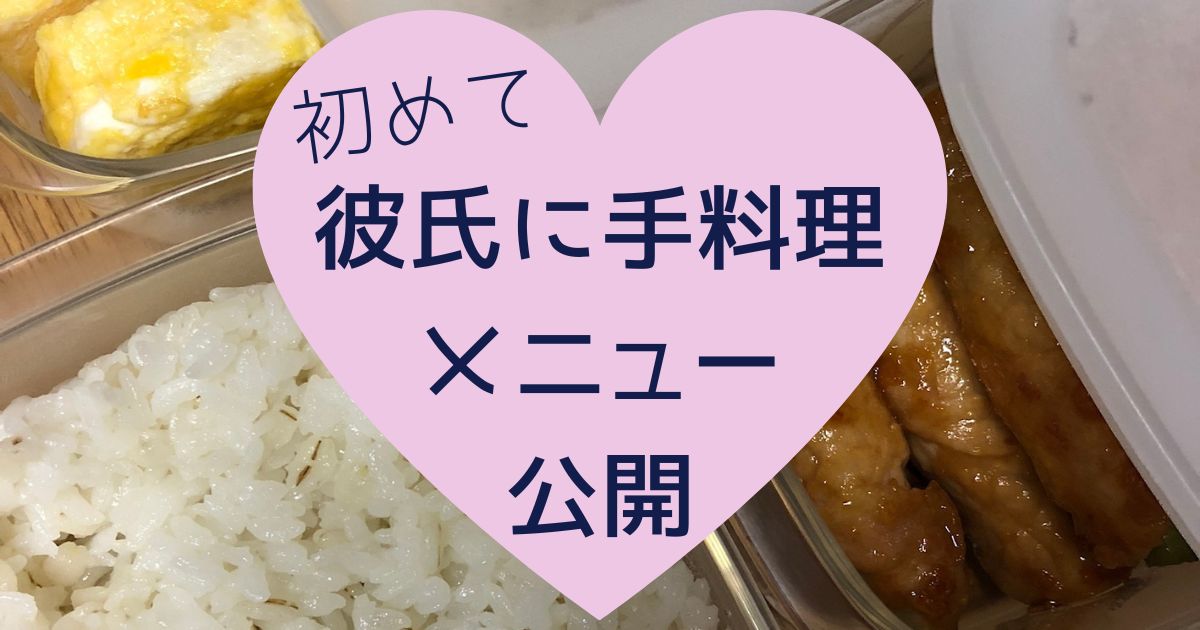
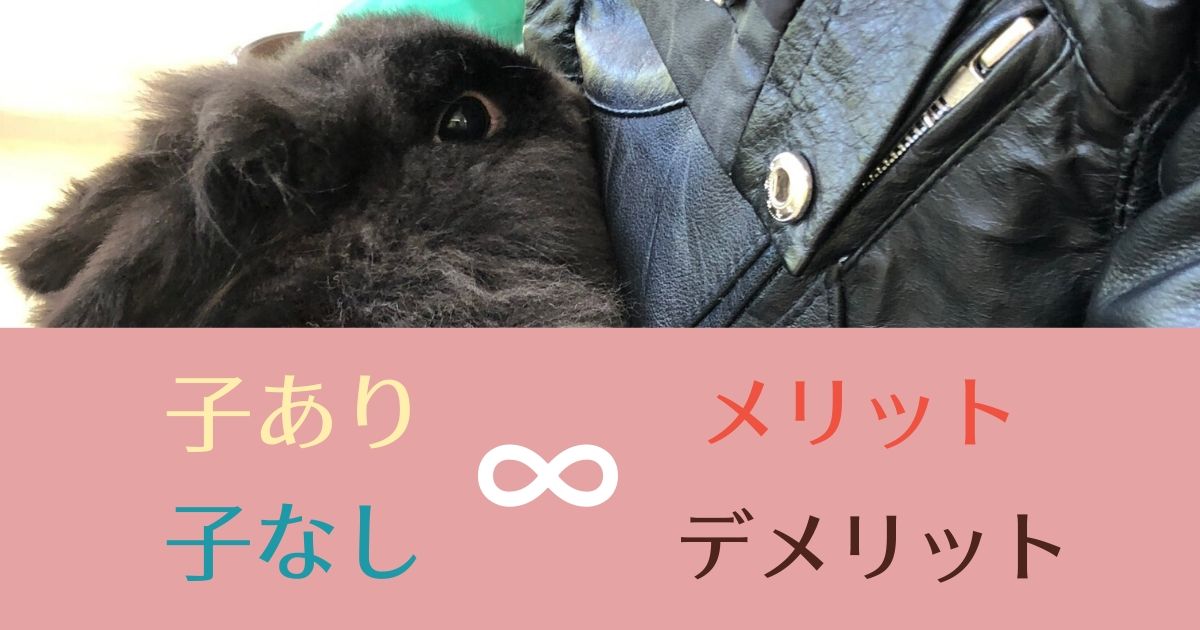
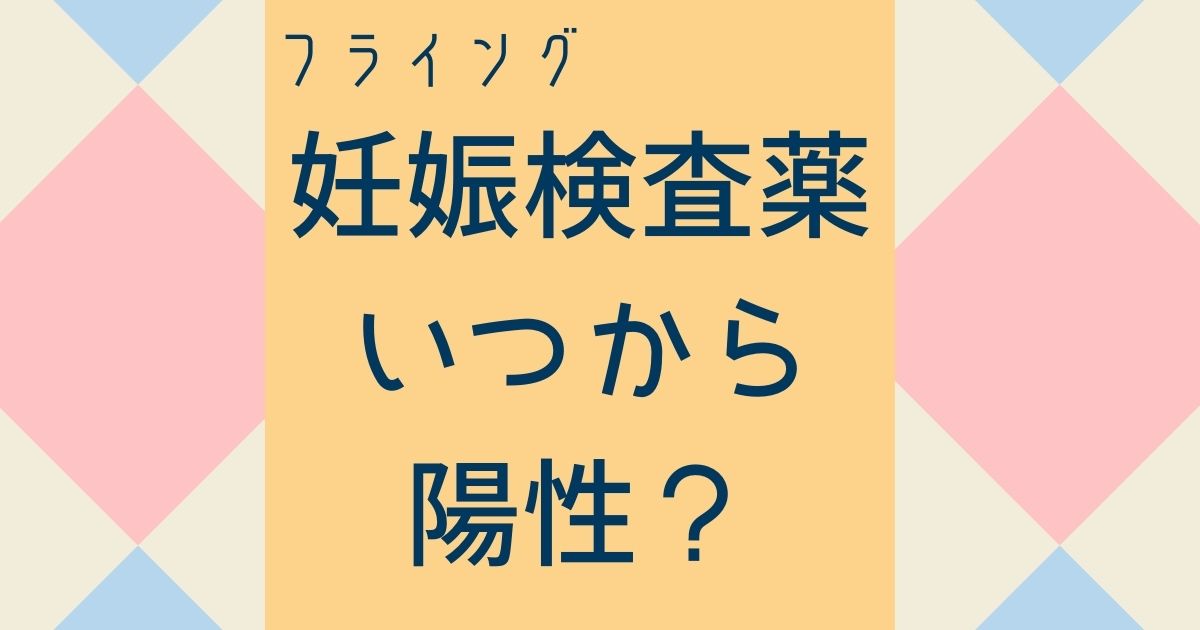
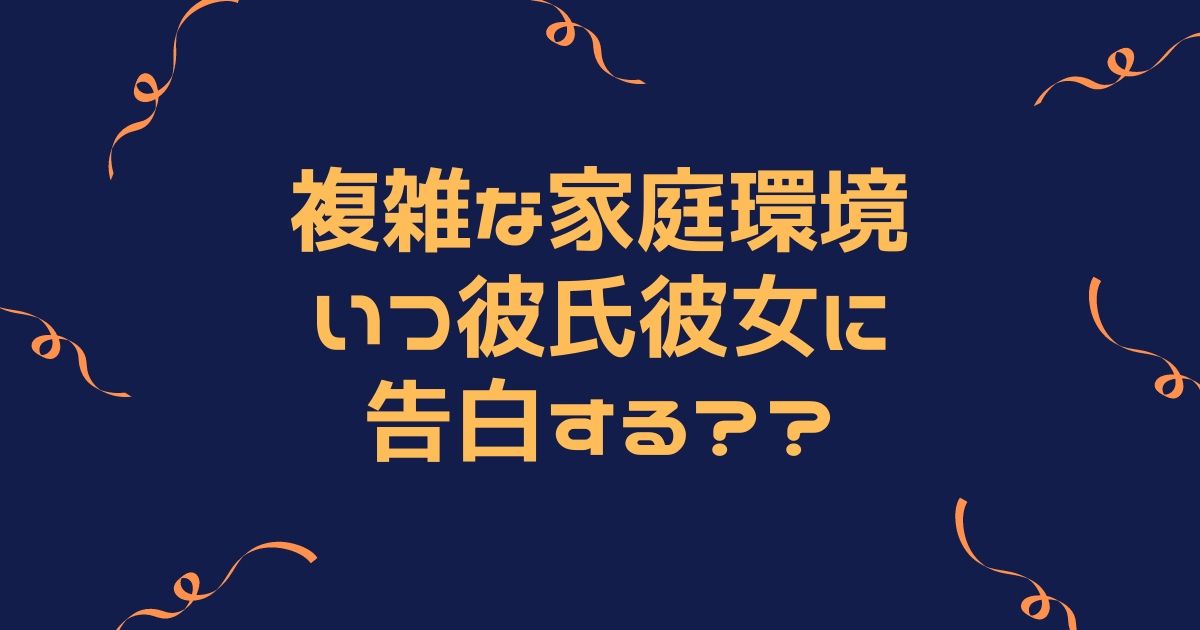
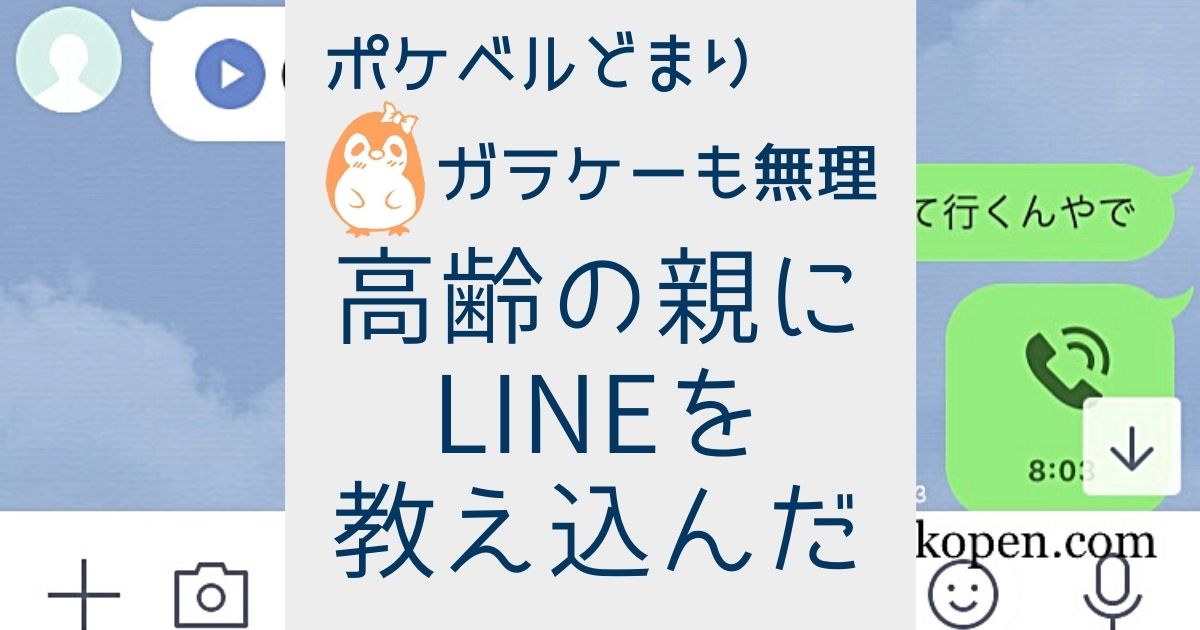

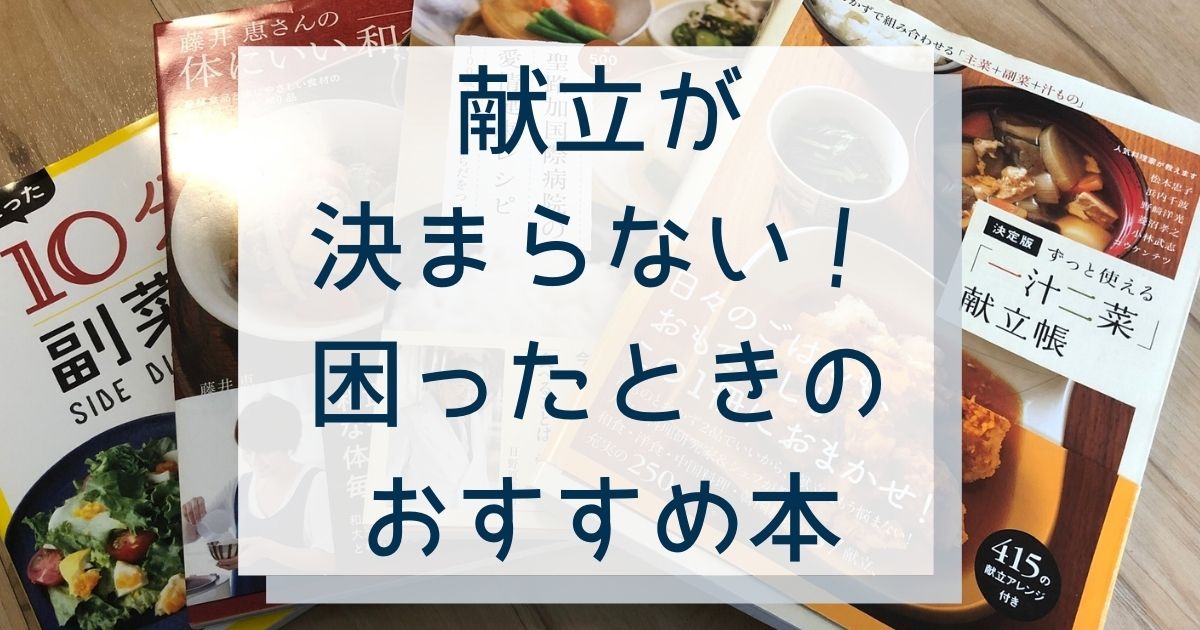








コメント